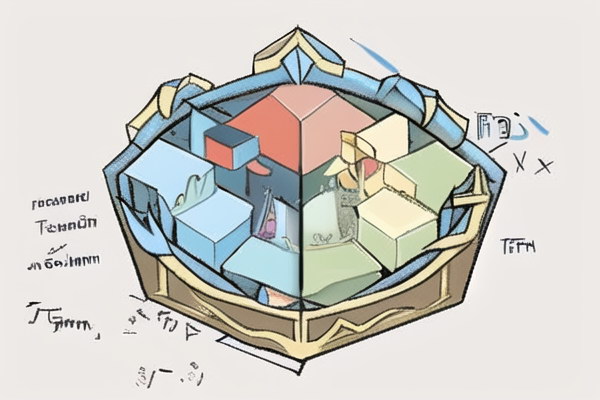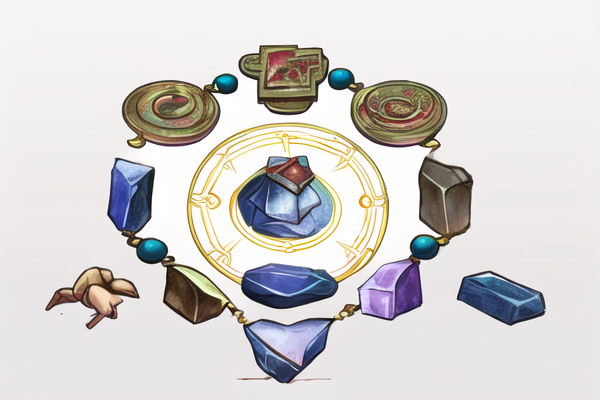幽夢の淵から抱かれた僕の骨灰
「夜が深まるにつれて、夢の世界が次第に現実のようになってくる。ある日、僕はそのような夢を見た。その夢は、まるで現実のようで、またまるで現実とは異なる不思議なものだった。
夢の中で、僕は自分の骨灰を抱かれていた。その骨灰は、まるで柔らかい布のような手触りで、重い心の重みを感じさせながらも、何かしらの安らぎを感じさせていた。周囲には、深い森が広がり、遠くには星が輝いていた。
骨灰を抱いているのは、僕の昔の友人だった。彼は、僕のことをよく知っていたように見えた。しかし、彼の顔には、何かしらの不気味な微笑みが浮かんでいた。まるで、死の香りを感じさせる微笑みだった。
「もう一歩、僕を待っている場所に行こうか」彼が僕に声をかけた。その声は、まるで深い淵の底から湧き上がってくるような感覚を持たせていた。
僕はためらいながらも、彼の手を握った。彼の手は、まるで冷たく、しっかりとした力を持っていた。その手を握ることで、僕はある決意をした。それは、この夢の世界を離れ、現実世界に戻ることだった。
しかし、その決意が固まった瞬間、僕の足は何故か止まった。彼の手が僕の心に深く刻まれたように、彼の言葉も僕の心に響き渡った。
「僕たちの友達、まだ生きている間に、最後の言葉を伝えておこう。」
彼の言葉に、僕は一瞬の沈黙を挟んだ。そして、その沈黙の中で、僕は何かを感じ取った。それは、僕たちの友情が、死をも超えて続いているという証拠だった。
「ありがとう、僕の友達。」僕は声を低く、心からの感謝の言葉を伝えた。
その言葉が響く間、夢の中の森は一瞬明るくなり、星もより明るく輝いた。そして、僕の目が覚めた。
現実世界に戻った僕は、その夢が何か意味を持つことを感じた。それは、僕たちの友情が、死をも超えて続いているという証拠であり、僕の心に深く刻まれたものだった。
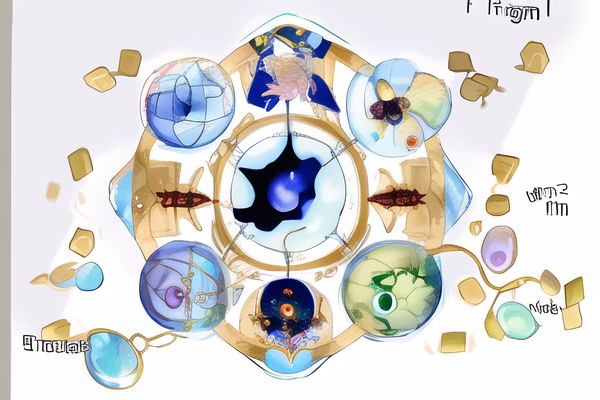
僕の骨灰を抱いたその夢は、僕にとって大切なものを教えてくれた。それは、友情が深いほど、その重みも大きいということだ。そして、その重みを感じながらも、僕たちは一歩一歩前進し続けていくのだと教えてくれた。
幽夢の淵から抱かれた僕の骨灰は、僕にとってかけがえのないものとなった。それは、僕の心に刻まれた、永遠の友情の証拠なのだ。」